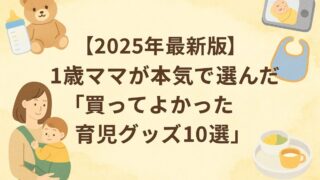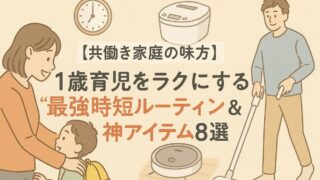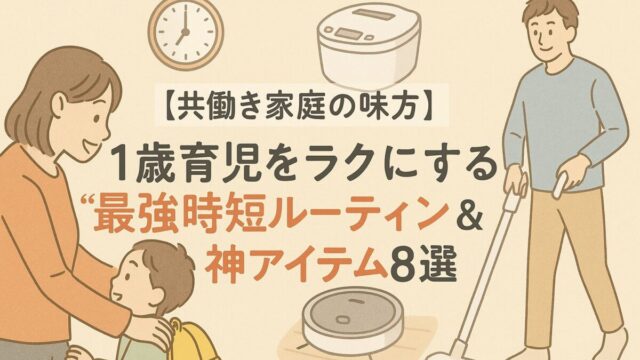「せっかく栄養バランスを考えて作ったのに、一口も食べてくれない…」 「うちの子だけ偏食がひどいのでは?」
幼児食が始まり、お子さんが1歳半〜2歳になると、多くの親御さんが「食べムラ」や「偏食」という壁にぶつかります。時間と愛情をかけて作ったごはんを拒否されると、イライラしたり、罪悪感を覚えることもあるでしょう。
しかし、安心してください。食べムラは、お子さんの成長過程で自然に起こる「自立と発達のサイン」です。
この記事では、管理栄養士の視点から、「食べない」行動の本当の原因を解き明かし、保育士の現場でも実践されている具体的な解決策と親の心のゆとりを保つための時短戦略をご紹介します。
これを読めば、食卓でのイライラが減り、自信を持って幼児食を進められるようになります。
1. 幼児食の「食べない」原因は4つの成長サイン

「食べない」原因は、単なるわがままではありません。1歳半ごろから見られる偏食や食べムラは、お子さんの心と体が大きく成長している証拠です。
原因1:成長の鈍化による自然な食欲減退
赤ちゃん期(0歳)は体が急速に成長するため、大量のカロリーと栄養を必要としました。しかし、1歳を過ぎると成長スピードが緩やかになるため 、それに伴い自然に食欲が落ち着きます。
【対策】
- 「離乳食期と同じ量を食べさせなきゃ」という焦りは不要です。
- 前の日より食べなくても、1週間単位で栄養バランスが取れていればOKと考えましょう。
原因2:遊び食べは「手先の発達」のサイン
手づかみでぐちゃぐちゃにする、食器を叩く、食べ物を落とす…これは「遊び」ではなく、「食べ物と手の使い方を学習している」段階です。
【対策】
- 手づかみメニュー(おにぎり、スティック野菜など)を積極的に取り入れ、「思う存分やらせてあげる時間」を作りましょう。
- 遊びがエスカレートしたら、静かに食事を下げて次の食事やおやつまで食べ物を与えません。これは、「食事の時間=食べる時間」という区別を学習させることを目的としています。
原因3:偏食は「味覚・嗅覚の発達」の現れ
特定の食材(特に野菜の苦味やネバネバ)を拒否するのは、味覚や嗅覚が発達し、食に対する警戒心が強まっているサインです。
また、新しい食材に対して警戒心を持つことは、人類が生き残るための本能(ネオフォビア)でもあります。
【対策】
- 嫌いなものは無理に食べさせず、「一口分だけお皿に乗せておく」だけでもOK。食卓に慣れさせることが大切です。
- 調理方法を変え、素材の味を極力感じさせない工夫(ポタージュ、ホワイトソースに混ぜるなど)をしましょう。
原因4:集中力の欠如(ダラダラ食い)
食事以外におもちゃやテレビに気を取られ、食べることに集中できていない状態です。1歳半以降は脳の発達により興味の対象が広がります。
【対策】
- 食事時間は30分までと区切り、テレビやスマートフォンは消しましょう。
- 集中力が続く午前中のおやつや、ランチでしっかり食べさせ、夕食は少し控えめにするのも一つの手です。
2. 専門家も実践!「食べムラ」を克服する具体的な声かけと環境づくり

ここでは、親御さんのイライラを減らし、お子さんの「食べたい気持ち」を引き出すための具体的なテクニックをご紹介します。
対策1:「完食主義」を手放す魔法の声かけ
「全部食べなさい」はNGです。子どもはプレッシャーを感じると余計に食べるのが嫌になります。
| NGな声かけ | OKな声かけ | 効果 |
|---|---|---|
| 「ほら、早く食べなさい!」 | 「わー、このにんじん、いい色だね!」 | 食べ物への興味を促す。 |
| 「残すと大きくなれないよ」 | 「この一口、頑張れたね!えらい!」 | 達成感と自己肯定感を育む。 |
| 「全部食べてから遊んでいいよ」 | (食べ終わった後の遊びを具体的に)「ご飯が終わったら、一緒にブロックで遊ぼうね!」 | 食事の後の楽しい見通しを持たせる。 |
対策2:見た目のハードルを下げる「隠しワザ」
偏食対策は、「いかに気づかせずに食べさせるか」がカギです。
- 野菜はポタージュ・スムージーに: 葉物野菜やブロッコリーを、甘いバナナや豆乳と混ぜて、おやつ感覚で飲めるようにしましょう。
- 細かく刻んで団子に: 苦手なひじきやキノコは、細かく刻んで肉団子やハンバーグに混ぜて、味をうまく隠してしまいましょう。
- 調理は「焼く」より「煮る・蒸す」: 野菜の苦味や臭みは、油で炒めると際立つことがあります。甘みが出やすい煮込み料理や蒸し料理に変えてみましょう。
対策3:「食育」を意識した環境づくり
食べ物を特別なものとして意識させる環境を作ります。
- 一緒に作る: 1歳半でも、レタスをちぎる、豆腐を混ぜるなど、簡単な作業を「お手伝い」としてやらせることで、食事への関心が高まります。
- 食器にこだわる: 子どもが好きなキャラクターや、カラフルで楽しい食器を使うと、食事が遊びの延長線になり、進みが良くなることがあります。
3. 幼児食の偏食で悩むママ・パパの救世主

偏食対策の工夫は大事ですが、毎日それを続けるのは大変です。親が疲れてしまうと、食卓がストレスになってしまいます。
ここでは、親の負担を劇的に減らしつつ、子どもの栄養をしっかり確保できる「心のゆとり」を持つためのとっておきの戦略をご紹介します。
救世主1:【収益導線】栄養バランスが完璧!偏食対策ミールキット・宅配食材
「苦手な野菜を細かく刻む」「栄養バランスを毎日計算する」という手間から解放されるのが、幼児食向けに特化した宅配食材サービスです。
管理栄養士が監修しているため、調理の手間をかけずに、子どもの成長に必要な栄養素を確保できます。
✅ 特に幼児食の偏食に悩む方におすすめのサービス
- Oisix(オイシックス): 献立キットのミールキットが有名。献立に悩む時間がなくなり、調理時間も短縮できます。
- パルシステム: 幼児食用の冷凍食材やアレルゲン配慮の商品が充実しており、安全性が高いです。
- TEDEMOGU(てでもぐ): 手づかみ食べ用の冷凍離乳食です。管理栄養士が監修しており、鉄分やたんぱく質・食物繊維を意識したメニュー展開になっています。

救世主2:外出時や非常時の頼れる味方!市販のベビーフード・レトルト
「手作り神話」に縛られる必要はありません。市販の幼児食レトルトは、栄養基準を満たしており、味付けも子どもの発達段階に合わせて調整されています。
外食時や、親の体調が優れない時、忙しすぎて料理ができない時に「罪悪感なく」頼れるレトルトを常備しておきましょう。
4. まとめ:栄養士からのエールと次のステップ

幼児食の「食べムラ・偏食」は、決して親のせいではありません。それは、お子さんが「自分の好き嫌いを主張し始めた」という、自立への一歩です。
完璧な栄養バランスを目指すよりも、「親が笑顔で食卓にいられること」が、お子さんにとっては何より大切です。
焦らず、できることから一つずつ対策を取り入れてみましょう。
✅ 最後にチェック!
最も負担の大きい献立決めと調理の手間を減らすことが、食卓のイライラを解消する最速の方法です。
「親のゆとり」を作るための投資として、ぜひ宅配食材サービスをチェックしてみてください。
関連記事